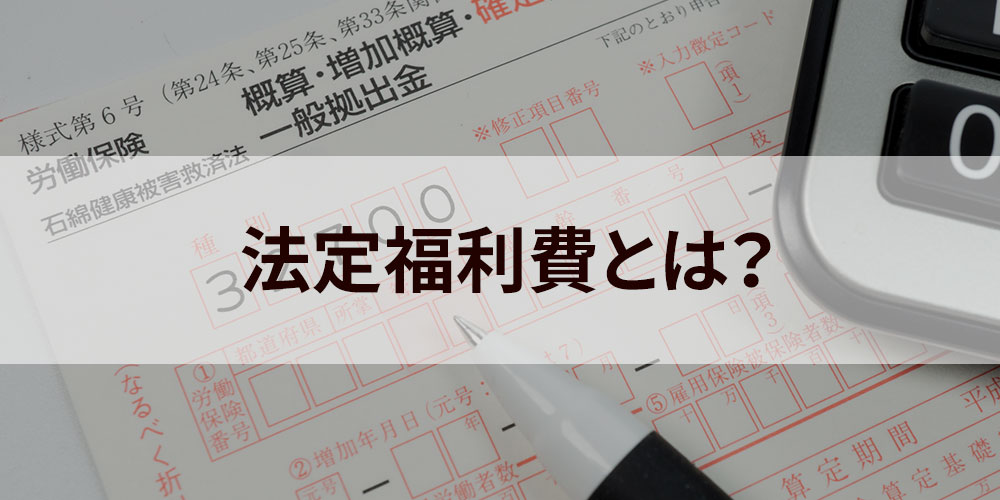ニュース 法定福利費の上限はいくらですか?. トピックに関する記事 – 法定福利費の月の平均額はいくらですか?
中小企業が導入している「法定福利費」の平均額
2020年12月に発表された「第64回 福利厚生費調査結果報告」によると、2019年度の中小規模企業の法定福利費は従業員一人当たり平均75,076円 / 月でした。交通費や食事補助など項目別に上限が定められているものもありますが、原則福利厚生費全体の計上に上限金額はありません。法定福利費について調べていると「企業の負担率16%」という言葉を耳にすることは多いかもしれません。 事業者の社会保険料の負担率は、合計すると約15%です。 社会保険と労働保険の事業者負担部分の保険料率を合算したときは約16%になります。
法定福利費は見積に含めるべきですか?下請企業に工事を発注する場合は、下請企業の法定福利費も含めて見積書を作成す るのでしょうか。 A. 下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者 に対する見積書を作成してください。
法定福利費はどうやって計算するのですか?
法定福利費は、一般的に労務費を賃金とみなして算出します。 厚生年金保険、健康保険、介護保、雇用保険険、子ども・子育て拠出金、それぞれの保険料の事業主負担割合を労務費に掛けて、法定福利費を算出します。2021年(令和3年)の「建設の事業」にかかる雇用保険料率では、事業主負担分は0.8%になります。 この保険料率を労務費にかけた金額が、見積書に明記する法定福利費です。 また、法定福利費の算定方法には労務費と同様、過去の実績から工事あたりの法定福利費の平均割合を算出し、それを用いて概算計上することも認められます。
福利厚生費の一人当たりの上限はいくらですか?
法律で定められた福利厚生を法定福利といい、それ以外の福利厚生を法定外福利といいます。 法定福利、法定外福利は基本的に非課税です。 そのため、従業員のために使う費用はできるだけ福利厚生費に計上したいと考える企業は多いです。 福利厚生費には上限はないものの、下記のように項目によってはさまざまなルールがあります。
福利厚生は前提として従業員が平等に利用できなければなりません。 従業員の歓送迎会などの飲食代、社員旅行の費用、スポーツジムなどの施設の利用料など、すべての従業員を対象に含めてください。 役員だけの飲み会、従業員の半数以下の旅行などの場合は福利厚生とは認められず、課税対象になってしまいます。
見積書に法定福利費の明示が必須になったのはいつからですか?
平成24年11月に国土交通省土地・建設産業局より施行された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が平成28年7月に一部改正され、見積書に法定福利費の内訳明示が必須となりました。建設業における法定福利費について
工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合=法定福利費工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費=法定福利費保険料率については、協会けんぽや年金機構のウェブサイト等で確認できます。雇用保険料率は、厚生労働省が年度ごとに発表しており、全国一律です。 2021年(令和3年)の「建設の事業」にかかる雇用保険料率では、事業主負担分は0.8%になります。 この保険料率を労務費にかけた金額が、見積書に明記する法定福利費です。
法定福利費(事業主負担分)=賃金総額×労災保険料率(注)%×事業主負担割合1/1となります。 (注)労災保険料率は、業種によって細かく分かれています。 令和3年度の建設事業では、水力発電施設、ずい道等新設事業62%、道路新設事業11%、舗装工事業9%などとなっています。
福利厚生費として認められる範囲は?福利厚生費として認められるには、事業者が従業員のために支出した費用が、一部の人だけでなく従業員全員を対象とするものである「機会の平等」、支出する金額が常識的に考えて妥当な範囲である「金額の妥当性」という2つの条件を満たしている必要があります。
福利厚生費は税金を払わなくていいの?福利厚生費は非課税のため課税率は0%ですが、もしも福利厚生費として妥当でないと判断された場合には、給与を支給したという扱いになるため、所得税を課税されることになります。 福利厚生費が給与扱いに変わると、源泉所得税漏れがあったと判断されます。
福利厚生費として認められるのは何泊まで認められますか?
福利厚生費として社員旅行の費用を計上するには、社員旅行の期間も重要です。 4泊5日以内であることが条件とされますが、海外旅行における機内泊は宿泊日数にカウントされません。 機内泊を除いた、海外に滞在する期間が4泊5日以内であれば、問題なく経費として扱えます。
旅行期間が4泊5日以内、かつ全従業員の50%以上が参加している、金額が社会通念上妥当であることを条件として、福利厚生費として認められます。法定福利費は値引きの対象外です。令和5年度は、5.000%(東京都の事業主負担分)でした。