ニュース 「御前を退く」とはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 「御前を退き」とはどういう意味ですか?
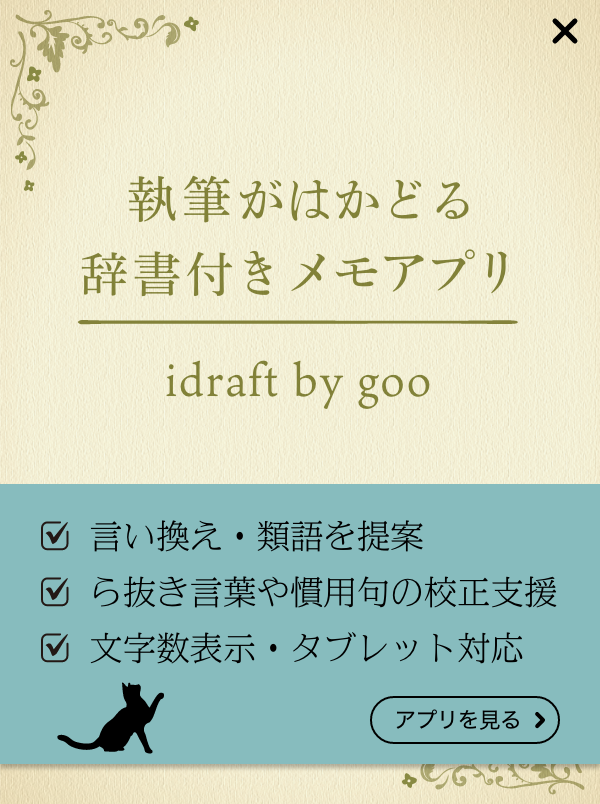
2 ㋐貴人・目上の人の前を離れて出て行く。 退出する。 また、その場所から去る。 「御前を—・く」「控えの…お‐まえ〔‐まへ〕【▽御前】
[代]《古くは目上の人に対して用いたが、近世末期からしだいに同輩以下に用いるようになった》二人称の人代名詞。 2 近世前期まで男女ともに目上の人に用いた敬称。 あなたさま。の・く【▽退く】
- 今までいた場所から離れる。 今までの場所をあけて他へ移る。 どく。「
- ある場所から離れている。 へだたっている。「 現場から少し―・いた所」
- 地位・職務から離れる。 引退する。「 大学教授を―・く」
- 組織や仲間から抜ける。 脱退する。「
- 今までの関係を離れる。 縁が切れる。「

引くと退くの違いは何ですか?ひき‐の・く【引き▽退く】
[動カ四]引きさがる。 退去する。 [動カ下二]「ひきのける」の文語形。
御前 誰を指す?
[代]二人称の人代名詞。 1 高位高官の男性を敬っていう。 2 婦人を敬っていう。 3 近世、大名・旗本、また、その妻を敬っていう。お‐まえ〔‐まへ〕【▽御前】
[代]《古くは目上の人に対して用いたが、近世末期からしだいに同輩以下に用いるようになった》二人称の人代名詞。 2 近世前期まで男女ともに目上の人に用いた敬称。 あなたさま。
「御前」は「ごぜん」と「みまえ」のどちら?
御前(ごぜん・おんまえ・みまえ) – 「前」・「面前」の丁寧語。 御前会議(ごぜんかいぎ)など。 キリスト教では「みまえ」が使われる(きよしこの夜の日本語歌詞)。 御前(ごぜん) – 貴人・住職などの尊敬語の一つ。
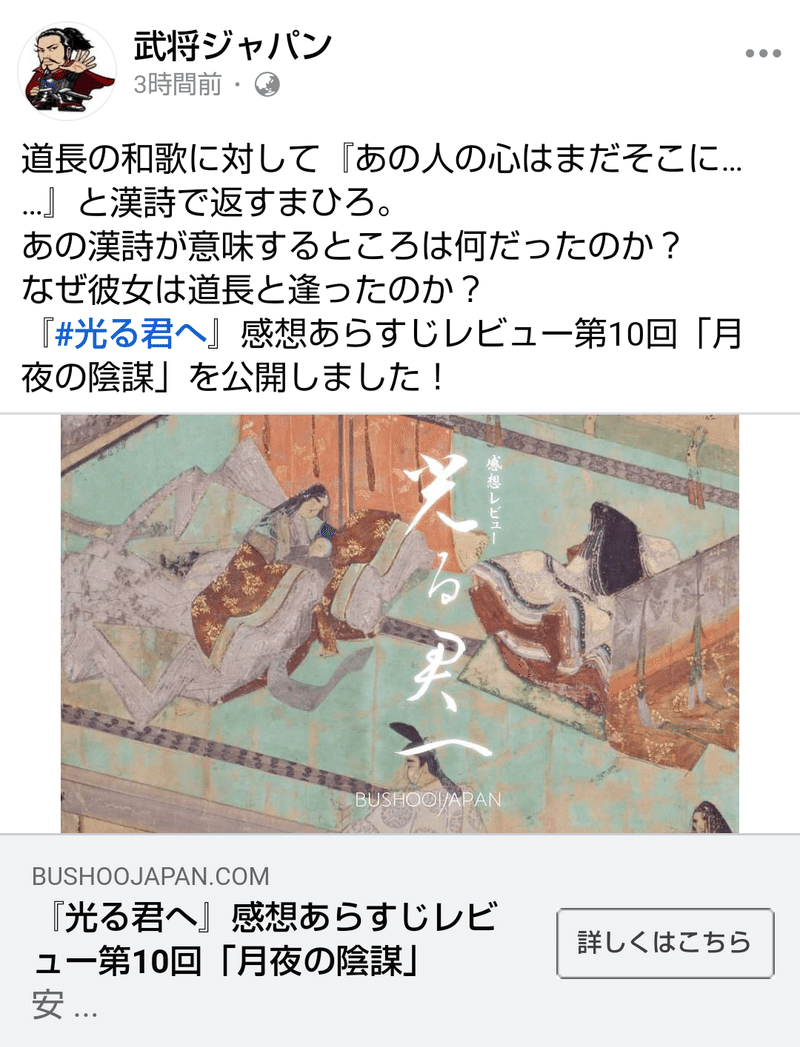
[代]二人称の人代名詞。 1 高位高官の男性を敬っていう。 2 婦人を敬っていう。 3 近世、大名・旗本、また、その妻を敬っていう。
「退く」の言い換えは?
自発的に(仕事、役職、位置)を去る の意
- 辞職
- 辞す
- 退陣
- 辞する
- 降りる
- 辞める
- 辞任
- 退身
退任 「退任」とは、現在の職務や任務を、自分から辞めることです。 「勇退」とは異なり、ほかの人から辞めることをお願いされた場合にも使用できる表現です。 たとえば、会社で役職に就いている人や、行政機関で働く人などが辞める際に用いられることが多いでしょう。いん‐たい【引退】 〘名〙 役職、地位から退くこと。 また、スポーツなどで現役から退くこと。

巴御前はその軍勢の中に駆け入り、御田八郎に馬をぴったりと並べ、彼をむんずとつかんで馬から引きずり落とし、自分の馬の鞍の前輪に押し付けて相手を身動き取れない状態にし、首をねじ切って捨ててしまった。 その後、巴御前は武具を脱ぎ捨て、東国の方へと逃げて行った。 おそらく巴御前の思いはこうだったのではないでしょうか。
日本三大御前とは誰ですか?静御前、巴御前とともに日本三大御前の一人としてあげられ鎌倉幕府の正史である「吾妻鏡」に登場しますが、女性のそれも敵方の武将が記録される事は非常に珍しく、それだけで彼女の存在と活躍が鎌倉武士達に強い印象を与えたと言えます。
「御前」の使い方は?[名]
- 貴人・主君などの座の前、または、面前。 おまえ。 おんまえ。 みまえ。「 陛下の 御前 で演奏する」
- 神仏や神社仏閣を敬っていう語。 また、神主・住職を敬っていう語。 「わしが死んでも―さんに相談して」〈康成・十六歳の日記〉
- 貴人や高位の人の敬称。 また、その妻の敬称。
静御前はなぜ御前と呼ばれたのでしょうか?
静御前とは いったい「御前」とは、白拍子と呼ばれた舞や歌を生業とする女性を指すようです。 巴や静はそうした女性で、武将の側室として身の回りの世話をやいたのでしょう。 平家一族を討ち果たし、敵の大将親子を引き連れて東へ向かう義経を、頼朝は寸前の「腰越」に留め置いて鎌倉入りを許しません。
お‐めえ【御前】 〘代名〙 (「おまえ(御前)」の変化した語。 「おめい」とも) 対称。 現在では対等以下に用いるが、江戸時代には、男女ともに用い、目上の相手に用いることもあった。「辞める」を謙譲語で表現すると、「辞めさせていただく」になります。 目上の人に辞めたい意思を伝える場合は「誠に勝手ながら」や「申し訳ありませんが」と言葉を添えると、相手に誠意が伝わりやすくなります。 例えば、「誠に勝手ながら3月末で、バイトを辞めさせていただきます」と伝えるのも1つの手段です。「退職」という言葉を使うときは、自発的に会社を辞める場合だけでなく、定年退職や免職で会社を辞めた場合なども含みます。 一方で「辞職」は自らの意思で仕事を辞めることをいいます。 一般社員の場合には使われず、役員以上の役職者が辞めるときに使われることが一般的です。
