ニュース 援助者に求められる自己覚知とは?. トピックに関する記事 – 援助者の自己覚知とは?
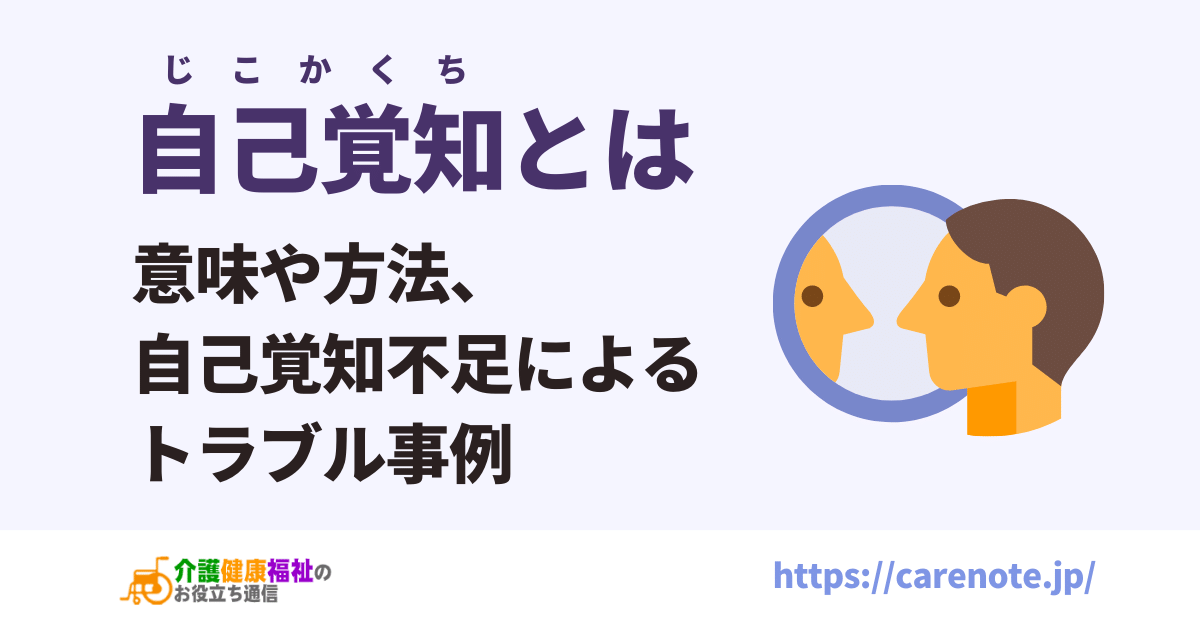
自分を知るとは、専門用語では「自己覚知」と言います。 一般に自己覚知は、援助者が自らの性格、個性を知り、感情、態度を意識的にコントロールすることで、援助者の価値観や感情に左右されない援助を提供するために重要とされています。 援助者は、自らを知り、必要なコントロールをしなければなりません。他者に対する自分の考え方や対応の根拠がどこにあるか、どうしてそのような対応をする自分があるのかを可能な限り客観的に自覚し、感情や態度をコントロールすること。 社会福祉援助技術の基本的な考え方の一つ。自己覚知をすると、自分の感情の変化や反応を客観的に理解し、予測できるようになります。 自分がどんな価値観を持っているのかや、誰かを支援する上でそれがどのように相手に作用するのかを理解しておくことで、自分の身体と心のバランスを保ち、援助者としての役割を適切に果たすことができます。

自己知覚と自己覚知の違いは何ですか?(2)自己理解の方法 自己理解の過程は①自分を客観視する(自己知覚)②自分自身の現実を受け入れる(自己受容)③深く自分について分析をする(自己洞察)④自分の経験則や体験による内的感情を自覚する(自己覚知)であるとされている。
自己覚知とはどういう意味ですか?
自己覚知とは、自分自身の内面に入り込んで自分を知る作業です。 そして、自分自身の価値観や人間性が、他人に良くも悪くも大きな影響を与える場合があるということを知ることです。サービス利用者(クライエント)に対して、支援する立場の人。 ソーシャルワーカー、ケースワーカー、グループワーカー、コミュニティワーカー、介護者、家族、ボランティア等の援助する人の総称。
自己覚知とは何ですか?
自己覚知とは、自分自身の内面に入り込んで自分を知る作業です。 そして、自分自身の価値観や人間性が、他人に良くも悪くも大きな影響を与える場合があるということを知ることです。
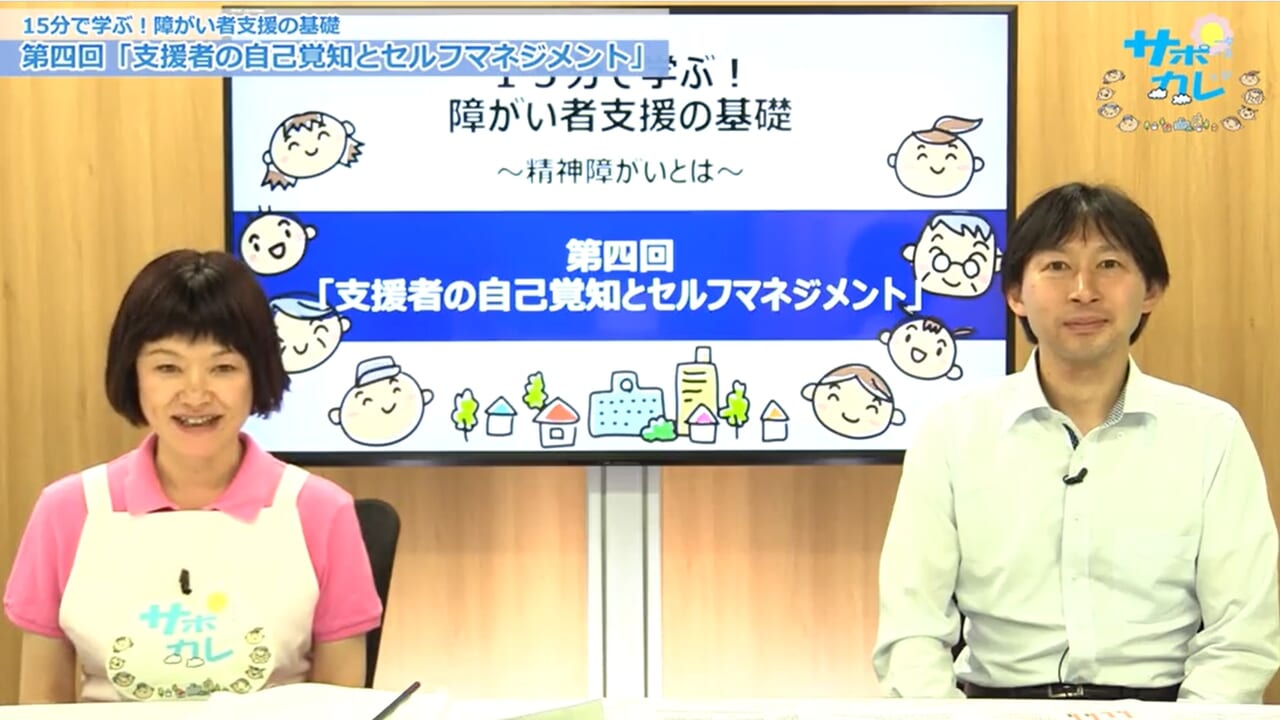
「自己覚知」の方法に決まった形はありません。 巷の心理テストから、友達との会話、自己の内省など、様々な機会をとらえて、要は自分の考え方のクセ、傾向、根っこを自覚することです。 「つい時間に遅れがち」といったライトなものから、「なぜ先生の仕事を選んだか」という根源的な問いまで含みます。
援助職とは何ですか?
援助の必要な人と実際にかかわって援助活動を行なっている人のことを対人援助職といいますが、多くの職種の人がいろんな分野で働いています。 医師や看護師ほかの医療職、教師や保育士、ソーシャルワーカー、地域や施設で生活指導に携わるケアワーカー、相談員や心理技術者…自己確 知ともいう。 普通、人間は他人をみるとき自分の 価値基準や感情に影響されやすく、しかも、その ことにみずから気づきにくい。社会生活を送るうえで身体的,精神的,社会的などの処要因によって何らかの解 決を要する生活課題に直面している個人や家族に対して,その問題解決や課題遂行を 援助するために,援助者によって用いられる援助技術。 利用者個人を主として考え, その環境に適応するために必要な援助を行って行く。

「支援」が他人の活動の一部を助けることを指すのに対し、「援助」は全面的にその活動を助けることを指しています。 支援をする人はあくまで脇役、最終的に行動する人は「支援をされる側」。 対して、「援助」をする人は主役。 できることが少ない人に対して主体的に動き、本人ができないことを代わりにやってあげることが援助です。
援助とはどういう意味ですか?援助/支援/後援/応援 の共通する意味
困難な状況にある人を助けること。
「覚知」とはどういう意味ですか?かく‐ち【覚知】
1 悟り知ること。 2 消防機関や警察が、火災や事件などを認知すること。
「援助者」とはどういう意味ですか?
サービス利用者(クライエント)に対して、支援する立場の人。 ワーカーとも言う。
かく‐ち【覚知】
1 悟り知ること。【覚知】悟りと知ること。 【隔地】遠く離れた所。 【確知】確実に知ること。「援助」の言い換え・類義語
- 力ぞえ
- 補助
- 扶ける
- 輔佐
- 手伝う
- 荷担
- 扶翼
- 輔翼
