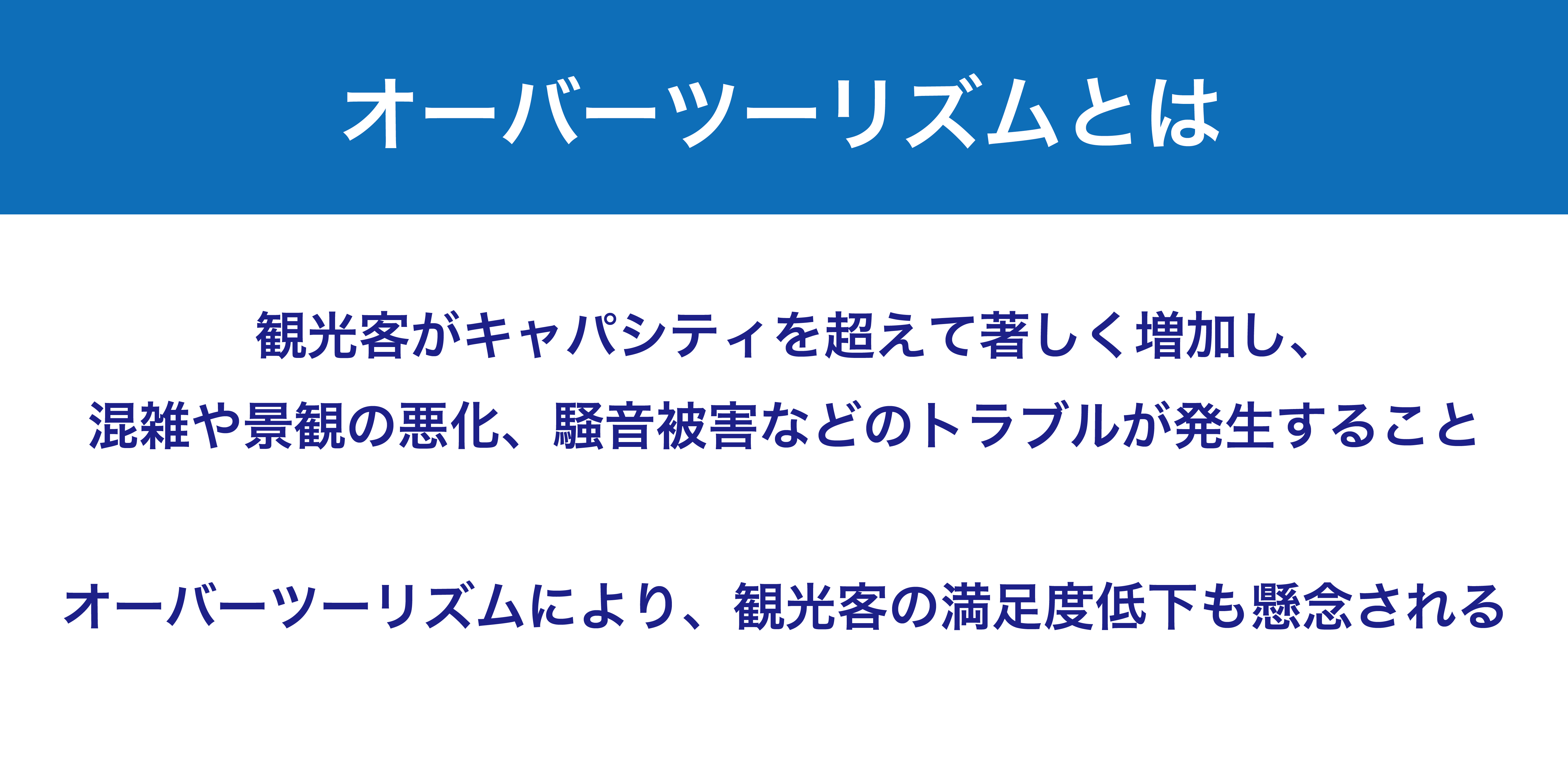ニュース 観光公害とオーバーツーリズムの違いは何ですか?. トピックに関する記事 – オーバーツーリズムの代表例は?
オーバーツーリズムとは、観光地にキャパシティ以上の観光客が押し寄せること。 具体的な問題としては、街中の人混みや交通渋滞、トイレの不足といったインフラの問題、騒音やゴミの問題、環境破壊などと、それらを原因とした地域住民と観光客とのトラブルが挙げられます。 日本では「観光公害」という表現が使われることもあります。オーバーツーリズム問題の現状
特に今問題視されているのが、旅行者が観光地などに集中することで起こる、「公共交通の混雑」や「ゴミの散乱」といったマナー問題などによる地域住民の生活への影響が出ており、日本国内では、京都、鎌倉、沖縄の石垣島、岐阜県の白川郷での観光公害(オーバーツーリズム)が目立っています。オーバーツーリズム(Overtourism)とは日本語で「観光公害」と言われ、特定の観光地において訪問客が増加することによって、地元住民の生活や自然環境、そして観光客自身にも悪影響を及ぼす状況のことを指す。
オーバーツーリズムと観光公害の違いは何ですか?すなわち、観光公害は、観光の「質」的な問題やそもそも観光が内包している負の側面の「総体」を含んだ概念であり、それに対してオーバーツーリズムは、観光客の「数」が増えること、あるいはそれによって生じる負の影響を指した概念であるという理解が可能です。
日本のオーバーツーリズムの例は?
オーバーツーリズム(観光公害) 日本国内3つの事例
- オーバーツーリズム事例① 京都のバス問題
- オーバーツーリズム事例② 宮古島の交通混雑や海の環境悪化問題
- オーバーツーリズム事例③ 鎌倉の「スラムダンク」聖地巡礼問題
オーバーツーリズムは、その地に暮らす人々に下記のようなネガティブな影響を与えています。
- 交通渋滞の発生や公共交通の混雑化
- ゴミ問題や騒音被害
- 観光客が私有地に無断で侵入する(プライバシーが侵害される)
- 地価や物価の価格高騰
- 観光地化により昔から暮らしていた住民や地域住民が営むお店が追い出される
- 犯罪の増加や治安の悪化
オーバーツーリズムはどこで起こっていますか?
オーバーツーリズムは、イタリアの水上都市ベネチアや、スペインのバルセロナなど世界各地で問題となっています。 国交省によると、日本各地でもオーバーツーリズムによる問題起きています。
オーバーツーリズム(観光公害) 日本国内3つの事例
- オーバーツーリズム事例① 京都のバス問題
- オーバーツーリズム事例② 宮古島の交通混雑や海の環境悪化問題
- オーバーツーリズム事例③ 鎌倉の「スラムダンク」聖地巡礼問題
オーバーツーリズム 何が問題?
オーバーツーリズムは、観光客の数が観光地のキャパシティを超えてしまい、さまざまな問題が発生することです。 観光客によるゴミ問題や騒音、公共交通機関の混雑などが例として挙げられます。サステイナブル・ツーリズムというと、オーバー・ツーリズムの反対概念、つまり観光客が多すぎるところに制限をかけて地域環境を保全するというイメージを持たれるかもしれません。「観光公害」というのは過度な観光客の集中によって観光地への負荷が懸念される事態を指します。 具体的には観光客を対象にした開発に伴う環境や景観破壊、文化財や遺跡への悪影響、交通渋滞や大気汚染、現地住民にとっての生活環境の悪化やプライバシーの侵害などがあります。
航空運賃の低下、旅行予約のデジタル化、SNSの普及により、以前は手の届かなかった観光地へのアクセスが向上しました。 これらの要因により、多くの人々が観光地を訪れるようになり、旅行者の数は増加の一途を辿っています。 これが、観光業の急激な成長とオーバーツーリズムの出現につながっています。
オーバーツーリズムによる環境破壊の例は?地域の生活環境の悪化
オーバーツーリズムによって、交通渋滞や混雑、騒音、無断駐車、ごみの不法投棄、立ち入り禁止区域への侵入、違法民泊、文化財の損傷などが問題視されている。 これらの問題は、地域住民の生活や地域の自然環境に悪影響を与える可能性も。
オーバーツーリズムで何が起こっているのか?世界の観光地で、観光客の増加による交通機関の混雑や交通渋滞、ゴミや騒音など生活環境の悪化が住民の反発を招いたり、自然環境保護のため人気の高いビーチが閉鎖されるなどの状況が発生している。
オーバーツーリズム いつから 日本?
ゴミの増 加、騒音、ヤミ民泊、レンタカー事故の増大、地価の上昇など問題は多岐にわたる。 こうした 状況を示す言葉として近年、「オーバーツーリズム」という表現が使用されるようになった。 2016 年 8 月に登場したこの言葉は、新しい概念でありながら、今観光地で起きている問題を 示す言葉として非常に注目されている。
オーバーツーリズムは、別名「観光公害」とも呼ばれており、観光地の住民生活と自然環境を守るためにも、必要な対策となります。 外国人観光客へのマナー啓発は、トラブルを防止するためにも、不快のないように、文化や風習の違いを伝える必要があり、なかなか難しいものです。私たち一般の人々にもオーバーツーリズムの問題解決に向けてできることがあります。 それは、訪れる観光地の環境や文化を尊重し、持続可能な観光を心がけることです。 具体的には、地元のビジネスを支援する、ゴミを適切に処理する、公共の場所での騒音を避けるなどの行動が求められます。5・1 四大公害病 日本は1950年代から60年代にかけて、未曾有の環境汚染とそれに伴う公害病を経験した。 なかでも、水俣病、イタイイタイ病、カネミ油症、四日市ぜん息(喘息)の被害が典型的である。 ※ 一般には、四大公害病は「水俣病」「新潟水俣病」「イタイイタイ病」「四日市ぜん息」を指すことが多い。